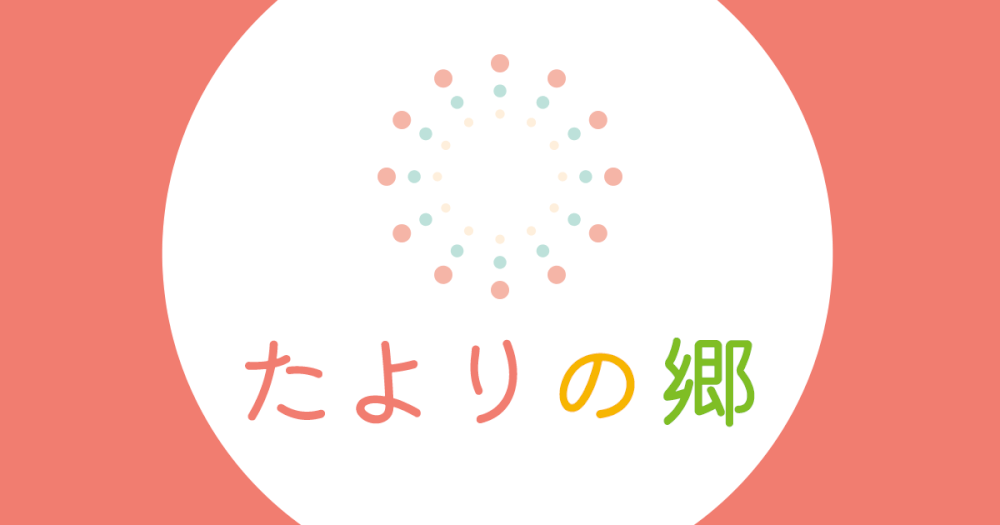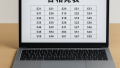「要介護3でもらえるお金」について調べたとき、「結局、いくらもらえるのか?」「自己負担額はどれくらいになるの?」と不安になった方も多いのではないでしょうか。
実は、要介護3で介護保険から支給されるのは【月額27万480円】が上限(2025年4月時点)で、この範囲内なら多くのサービスを自己負担1割で利用できます。ただし、所得状況によっては自己負担が2割・3割に増えるケースもあるため、費用負担は人それぞれ大きく変わります。
現金が「直接もらえる」と誤解されがちですが、実際には介護サービス利用時に『費用の一部を公的保険が補助する』という仕組みです。この上限を超えた分は全額自己負担になるため、家計へのインパクトも見逃せません。
「将来の費用が想定以上に膨らむのでは?」と心配な方こそ、この支給限度額と自己負担の最新ルールをしっかり知っておくことが重要です。
この記事では、具体的な自己負担例、在宅介護と施設入居時の費用差、公的補助の正しい活用方法まで、最新データや実際のモデルケースをもとに徹底解説します。
最後まで読むことで、「損をしないために今から準備すべきこと」が見えてきます。
要介護3でもらえるお金の基本理解と制度の誤解を正す
要介護3でもらえるお金とは?支給限度額とその本質をわかりやすく解説
要介護3の認定を受けると、介護保険制度を活用して介護サービスを受けることができます。しかし、よく誤解されがちな点として「現金がおりる」のではなく、所定の支給限度額内でサービス利用費の一部が公的に支給されるという仕組みになっています。2025年現在、要介護3の支給限度額は月額270,480円(地域やサービスによって変動あり)です。この限度額内で、1割から3割の自己負担でサービスを利用できます。支給限度額を超える部分は全額自己負担となるため、利用計画には注意が必要です。
現金給付と介護サービス給付の違いを具体例で理解する
現金給付とは、本人や家族が金銭を直接受け取るものですが、要介護3の場合は現金自体をもらうことはありません。介護保険の給付はほとんどが「サービス給付」です。たとえば、訪問介護やデイサービスなどの費用が支給限度額の範囲で補助される形になります。以下の表で主な違いを整理します。
| 給付の種類 | 内容 |
|---|---|
| 現金給付 | 本人や家族に直接お金が渡る |
| サービス給付 | 指定サービス利用時に費用が一部支給され、利用者は自己負担のみ支払う |
このため、「要介護3でもらえるお金=サービス費用の補助」と理解すると誤解が少なくなります。
要介護3でもらえるお金申請の基本的な流れと注意点
要介護3の支給限度額やサービス利用のためには、まず自治体へ介護認定の申請が必要です。申請の主な流れは下記の通りです。
- 申請書を市区町村窓口に提出
- 認定調査と主治医意見書の提出
- 審査判定を経て認定結果通知
- ケアマネジャーとケアプラン作成
- 利用開始
申請時は、必要書類の不備や情報の誤記に注意し、分からない部分は地域包括支援センターで相談してください。特に要介護3はサービス利用の幅が広いため、希望するサービス内容と自己負担額のバランスを事前に確認することが重要です。
自宅介護と施設入居で変わる費用構造と給付パターン
在宅介護の自己負担割合と補助制度一覧
在宅介護の場合、介護保険から支給されるサービス費用の自己負担割合は、原則1割、一定以上の所得がある場合は2割または3割です。ここで特に注目すべき補助制度は以下の通りです。
-
おむつ代助成(地域によって支給・支給限度額が異なる)
-
住宅改修費の支援
-
福祉用具の購入・貸与
自己負担額の具体例としては、270,480円の支給限度額までサービスを利用した場合、1割負担なら約27,000円、3割負担なら約81,000円程度となります。おむつ代や通所介護も申請や医療費控除を活用することで、実質的な負担をさらに軽減できる場合があります。
施設入居時の介護費用と補助の違い
施設入居(特別養護老人ホームなど)の場合、毎月の施設利用料に加え、食費・居住費など自己負担が発生します。この場合の主な費用構造は以下の通りです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 施設サービス費 | 介護保険適用・負担割合反映 |
| 食費・居住費 | 全額自己負担 |
| 日用品・おむつ代 | 一部助成や控除あり |
施設にもよりますが、要介護3の場合、月額の自己負担総額は5万円~15万円程度になることが多く、地域や施設タイプで変動します。また、低所得者向けに負担軽減特例や補助金も用意されているため、該当地域の福祉窓口で必ず確認しましょう。施設選びも大切なポイントの一つです。
支給限度額の具体的数字と自己負担の計算方法
要介護3の支給限度額と2025年最新データ
要介護3に認定された方が介護保険で利用できるサービスには、支給限度額が設定されています。2025年時点での支給限度額は月額270,480円です。この範囲内であれば、訪問介護やデイサービス、福祉用具レンタルなどを組み合わせて利用できます。
支給限度額27万480円の詳細と利用可能範囲
限度額内で利用可能なサービスは多岐にわたり、例えば以下のようなものがあります。
-
訪問介護(ヘルパー利用)
-
デイサービス(通所介護)
-
通所リハビリテーション
-
短期入所(ショートステイ)
-
福祉用具貸与や住宅改修
主なポイントは、利用可能なサービスの合計金額が支給限度額を超えない範囲でプランが組まれるため、無理なく必要なサポートを受けられるという点です。日常生活の介助からリハビリまで、ケアマネジャーと相談しながら最適なプランを作成しましょう。
「自己負担割合1割〜3割」の仕組みと所得に応じた負担例
介護保険サービスの利用者負担は所得により1割~3割に定められています。自己負担割合は「介護保険負担割合証」で確認可能です。
下記のテーブルで、負担割合ごとの月額自己負担例を紹介します。
| 負担割合 | 自己負担額/月(上限利用時) |
|---|---|
| 1割(一般) | 27,048円 |
| 2割(一定以上所得者) | 54,096円 |
| 3割(高所得者) | 81,144円 |
所得が増えると自己負担も増加しますが、多くの方は1割負担です。自身の負担割合は自治体から送られる「介護保険負担割合証」で必ず確認しましょう。
介護保険負担割合証の見方と確認方法
介護保険負担割合証には、自分の負担割合が明記されています。負担割合証が届いた場合、次のポイントを確認してください。
-
氏名や要介護度
-
負担割合(1割・2割・3割)
見分けがつきにくい場合は、区役所や市役所の介護保険担当窓口、もしくは担当ケアマネジャーに相談することもおすすめです。
限度額超過時の費用負担と高額介護サービス費制度の活用法
支給限度額を超えてサービスを利用した場合、その超過分はすべて全額自己負担となります。たとえば、月に31万円分サービスを利用した場合、超過分約4万円は100%本人負担になります。ただし、高額な介護サービス利用によって実質負担が増えるケースでは、「高額介護サービス費制度」も活用できます。
この制度は、1ヶ月の自己負担が一定額を超えた場合に超えた分が払い戻される補助制度です。所得や世帯状況に応じて上限が異なりますので、事前にチェックしておくと安心です。
所得段階別負担上限額の2025年見直しポイント
2025年からは高額介護サービス費の所得基準が見直されており、以下のような上限額が適用されます。
| 世帯区分 | 月額上限額 |
|---|---|
| 低所得世帯・市民税非課税 | 15,000円 |
| 一般世帯 | 37,200円 |
| 現役並み所得者 | 44,400円 |
これにより、支給限度額を超えてしまった場合でも、過剰な負担を軽減できるよう配慮されています。ご自身が該当する区分や手続き方法は、必ずケアマネジャーや自治体の窓口で確認してください。
要介護3の給付金・補助金・助成金の全体像
要介護3の認定を受けると、様々な給付・補助・助成制度を活用できます。介護保険から介護サービス費用の大半が支給されるだけでなく、多様な福祉用具や住宅改修、医療費控除や自治体独自の各種助成も利用できます。自身や家族の状況にあわせて、最適な支援を組み合わせることが重要です。
補助金・助成金の種類一覧と申請条件
要介護3の方が利用できる主な補助金や助成金の種類と、概要・申請条件を一覧で確認できます。
| 名称 | 概要 | 主な申請条件 |
|---|---|---|
| 介護サービス給付金 | 介護保険で要介護認定者の自己負担以外が支給 | 要介護3認定済 |
| 福祉用具購入費補助 | 特定の福祉用具購入費用の一部を支給 | 年間支給上限や認定あり |
| 住宅改修費用の支給 | 手すり設置など改修の実費を上限20万円まで | 要介護認定・事前申請が必要 |
| おむつ代助成・紙おむつ給付 | 自治体独自で要介護者に給付助成 | 市区町村で条件が異なる |
| 高額介護サービス費 | 自己負担上限を超えた場合に払い戻し | 所得等により上限額異なる |
申請時の注意点:
-
多くの制度はケアマネジャーや市区町村窓口を通じて申請します。
-
給付条件や上限額は自治体によって異なります。
福祉用具レンタル・購入費や住宅改修費用の支給制度
要介護3の場合、介護保険から福祉用具のレンタル・購入費や住宅改修費が支給されます。
-
福祉用具レンタル:
- 対象は車椅子、特殊寝台、手すりなど
- 月額レンタル費用の1~3割が自己負担
-
福祉用具購入費:
- 排せつ用品や入浴補助用品など、年間10万円まで
- 購入後、自治体に領収書を提出して払い戻し申請
-
住宅改修:
- 手すり設置、段差解消など最大20万円まで支給
- 改修内容と事前申請が必須
各サービスごとに定められた上限や申請手続きがあります。事前の確認が大切です。
おむつ代助成、自治体独自の支給制度の具体例
要介護3になると、排せつケアに伴うおむつ代の負担も増えます。各自治体で次のような助成制度が設けられています。
-
紙おむつ給付制度:
- 毎月定額(例:3,000円分)までおむつ支給
- 要介護度や住民税非課税など条件あり
-
おむつ代の医療費控除:
- 医師の証明書があれば医療費控除に申請可能
自治体ごとに助成金額や利用条件に違いがあるため、詳細は市区町村福祉担当窓口で確認してください。
高額医療・介護合算制度の概要と申請方法
高額医療・高額介護合算制度は、医療費と介護サービス費の両方の自己負担が一定額を超えた場合、上限を超えた分が払い戻される仕組みです。
-
医療費と介護費の自己負担を1年単位で合算
-
所得区分ごとに上限額を設定
-
上限を超えた分は市区町村へ申請すれば受け取れる
申請時は医療費と介護費の領収書が必要になることが多いため、保管しておきましょう。
医療費控除や障害者控除との違いと併用時の注意点
医療費控除や障害者控除と併用する際は注意が必要です。
-
医療費控除
- おむつ代や介護サービス利用料も控除対象になる場合がある
- 必要書類(医師の意見書、領収書など)が必要
-
障害者控除
- 市区町村で要介護認定が条件になる場合あり
- 年末調整や確定申告で手続き
併用することで負担を大きく軽減できますが、申請漏れがないよう専門家や担当窓口へ相談するのがおすすめです。
デイサービスとヘルパー利用の費用・回数の実態解説
要介護3デイサービスの料金体系と自己負担の目安
要介護3の方がデイサービスを利用する場合、介護保険の自己負担割合に応じて支払う金額が変わります。要介護3の1か月あたりの支給限度額は約270,480円です。デイサービスの利用料は、1割負担であれば比較的抑えられますが、2割や3割負担となると費用も高額になります。主な費用項目は以下の通りです。
| 負担割合 | 1回あたり(目安) | 月12回利用時 |
|---|---|---|
| 1割 | 約800円〜1,200円 | 約9,600円〜14,400円 |
| 2割 | 約1,600円〜2,400円 | 約19,200円〜28,800円 |
| 3割 | 約2,400円〜3,600円 | 約28,800円〜43,200円 |
また、食事代やおむつ代は保険適用外となり、実費が必要です。自宅介護の場合も、これらの費用計算が重要になります。
週3回利用など利用頻度別の費用シミュレーション
週3回ペースでデイサービスを利用すると、1か月で約12回程度の利用となります。1割負担で1回1,000円と仮定したケースのシミュレーションは次の通りです。
| 週あたりの利用回数 | 月利用回数 | 1割負担の月額 |
|---|---|---|
| 1回 | 約4回 | 約4,000円 |
| 2回 | 約8回 | 約8,000円 |
| 3回 | 約12回 | 約12,000円 |
| 5回 | 約20回 | 約20,000円 |
デイサービスには送迎や入浴、機能訓練などのサービスがセットで提供されますが、利用限度額を超えると全額自己負担となるため、月額費用の管理が不可欠です。
ヘルパー利用回数・サービス内容と限度額内の調整法
ヘルパー(訪問介護)は、掃除や食事、排せつ、入浴介助など多様なサービスが受けられます。要介護3の支給限度額の範囲内で、どのサービスに重点を置くかを検討することが大切です。利用回数や単価は以下のようになります。
| サービス区分 | 1回あたり(目安) | 利用回数の調整例 |
|---|---|---|
| 身体介護 | 約300円〜500円 | 週3回:月12回で3,600円〜6,000円 |
| 生活援助 | 約200円〜400円 | 週2回:月8回で1,600円〜3,200円 |
ヘルパーの回数やサービス内容は、ケアマネジャーと相談しながら利用限度額に適合するよう調整しましょう。限度額いっぱいまで合理的に組み合わせるのがポイントです。
送迎サービス料金や加算の事例紹介
デイサービスや訪問介護では、送迎や特定の機能訓練、医療的ケアなどに加算料金が設定されています。主な加算項目の例は下記の通りです。
| 加算名 | 目安額(1回) | 内容 |
|---|---|---|
| 送迎加算 | 約50円〜100円 | 自宅から施設までの往復送迎 |
| 入浴介助加算 | 約50円〜150円 | 入浴支援サービス |
| 処遇改善加算 | 利用金額の数% | 介護職員の処遇改善のための加算 |
加算は利用内容や地域、事業所によって異なります。各家庭の事情や必要サービスに応じてバランス良く利用し、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。料金の詳細や最新情報は、各自治体やサービス提供事業所で確認できます。
要介護3の平均余命・生活実態から考える費用と備え
要介護3の平均余命データと長期費用見通し
要介護3は日常生活で多くの介助が必要な状態で、平均余命はおおよそ4〜5年とされています。医療現場や福祉分野では要介護度別の平均余命を算出しており、下記のようなデータが参考になります。
| 要介護度 | 平均余命(年) | 主な生活サポート |
|---|---|---|
| 要介護2 | 5〜7 | 自立困難な動作あり |
| 要介護3 | 4〜5 | 介助ほぼ常時必要 |
| 要介護4 | 3〜4 | 高度な介護・医療管理 |
| 要介護5 | 2〜3 | 全面的な介護が必要 |
在宅・施設ともに費用の備えが重要です。要介護3の介護保険支給限度額は月約27万円。自己負担割合が1割の場合でも、毎月2.7万円は自己負担し、限度額を超えると全額負担になります。4年暮らすと100万円を超える出費もあり、長期の費用計画は欠かせません。
一人暮らしや在宅介護の現実的な課題と対策
一人暮らしの場合、日常生活のサポートが手薄になり、安心して自宅介護を続けるには以下のような課題が頻出します。
-
夜間の急変や事故のリスクが高くなる
-
排せつ、入浴、食事の介助が家族に大きな負担
-
デイサービスや訪問ヘルパーを増やしても限界がある
-
おむつ代や医療費、生活支援など経済的負担が増加
強調すべき対策ポイント
-
地域包括支援センターやケアマネジャーを活用し、介護サービスを最大限に利用
-
紙おむつ給付や福祉用具レンタルを申請し負担軽減
-
訪問看護や緊急通報システムの導入
在宅介護が難しいケースの判断基準と支援制度
家族や一人での在宅介護が無理と感じる場合、早めの判断が大切です。以下のケースでは特に福祉・医療機関への相談が推奨されます。
-
24時間見守れない
-
認知症の進行や介護者自身の体調悪化
-
経済的・精神的な負担増大
利用できる支援制度
-
介護保険の短期入所(ショートステイ)
-
自治体の在宅介護支援金や医療費控除
-
紙おむつ代助成・家族介護者向け相談窓口
施設入居の場合の種類別費用モデルと比較
施設入居を考える際には、主な施設ごとに料金やサービスの違いを知り、無理のない計画を立てることが大切です。
| 施設名 | 月額費用目安 | 自己負担額 | 主なサービス |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 8〜15万円 | 所得連動で低額負担可 | 生活介助全般、食事、排せつ、医療サポート |
| 有料老人ホーム | 15〜30万円 | サービス内容に応じて変動 | 生活支援・リハビリ等独自メニュー |
| グループホーム | 12〜18万円 | 認知症ケアに特化 | 少人数制・家庭的サポート |
特別養護老人ホーム、民間施設、グループホームの費用差
特別養護老人ホームは公的補助が充実し、所得に応じた負担軽減が可能です。有料老人ホームは独自サービスが多く、費用は高くなりがちですが、多様なニーズに対応。グループホームは認知症の方に特化した少人数ケアで、柔軟性・家庭的な環境が魅力です。
費用を比較する際は、自己負担限度額や経済的支援制度の活用、各施設のサービス内容・利用条件を確認しましょう。事前の見学や費用シミュレーションが予算管理と安心につながります。
要介護3のケアプラン策定例と費用負担の具体解説
ケアプランの基本構造と要介護3向けサービス組み立て方
要介護3は日常生活のほとんどを介助に頼る状態となり、自宅介護や施設入居を検討するケースが増えます。ケアプランは介護保険の認定結果を基に策定され、支給限度額内で利用サービスを組み合わせます。要介護3の場合、支給限度額は月額約270,480円です。この範囲内で訪問介護、デイサービス、福祉用具のレンタルなどを選択し、自己負担割合(1〜3割)で費用が決まります。
主なサービス構成の例を表にまとめます。
| サービス名 | 利用頻度 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 週3回程度 | 排せつ・入浴介助、身の回りの支援 |
| デイサービス | 週2~3回 | リハビリ、入浴、食事、社会交流 |
| 福祉用具レンタル | 月1 | 車いす・ベッドレンタル |
| 訪問看護 | 週1回 | 健康チェック・医療的ケア |
在宅・施設別ケアプランのモデルケースと費用分布
在宅介護では自宅でできる範囲の支援が中心となり、地域の訪問介護事業所やデイサービス利用が一般的です。一方で特別養護老人ホーム等の施設入居の場合、毎月の費用は入居一時金や生活費を含めて大きく異なります。
| ケース | 月額総費用(目安) | 自己負担額(1割・3割の場合) |
|---|---|---|
| 在宅介護 | 8~13万円 | 約8,000~39,000円 |
| 施設介護 | 15~20万円以上 | 約15,000~60,000円以上 |
在宅介護では介護保険の範囲を超えない限り、自己負担も管理しやすい強みがあります。施設の場合は、食費・光熱費・おむつ代など追加負担も発生します。
実際の介護現場からの体験談・費用管理の工夫
要介護3の家庭では、毎月の医療費やおむつ代、介護サービスの組み合わせ選択など予算管理に工夫を重ねています。例えばおむつ代は介護保険の助成や自治体の紙おむつ給付制度を活用して費用抑制が可能です。
費用管理の主な工夫
-
介護保険支給限度内のサービス利用に調整
-
おむつ代給付・医療費控除など制度活用
-
費用比較のため複数施設やサービスを検討
-
ケアマネジャーとこまめに相談し最適化
家族の声とよくある悩みを反映した事例紹介
家族の体験を通じて「在宅介護は費用を抑えやすいが、介護者の負担が大きくなる」という声が多く寄せられています。また、施設入居では手続きや費用面で戸惑うケースが目立ちます。
よくある悩みリスト
-
要介護3の介護費用が月を追うごとに増えて困った
-
デイサービスの利用回数調整が難しい
-
おむつ代や医療費控除の申請手続きに手間取った
-
ケアプラン作成に不安がある
このような時は、地域包括支援センターやケアマネジャーに早めに相談することで、負担軽減や費用の見通しを立てやすくなります。制度や給付内容の最新情報も定期的に確認することが、安心して介護生活を送るコツです。
法制度の最新動向と公的データによる透明性の確保
2025年の介護保険制度改正ポイントと影響
2025年の介護保険制度改正では、要介護3の利用者に関する支給限度額や自己負担割合の見直しが行われました。要介護3の場合、介護サービス費用の支給限度額は月額約270,480円となっています。自己負担割合は本人や世帯の所得によって1割・2割・3割のいずれかが適用されます。上限額を超過すると、以降のサービスは全額自己負担となる点にも注意が必要です。
改正によって、低所得者への負担軽減措置や在宅介護の支援強化、各種給付金の申請要件が明確化されました。要介護3と判定された方でも必要に応じて、デイサービスや訪問介護など多様なサービスが柔軟に利用しやすくなったことが特徴です。
主な改正ポイント
-
支給限度額の見直し・更新
-
所得による自己負担割合の明確化
-
低所得者・高齢単身世帯への追加支援の強化
-
地域密着型サービスやリハビリの利便性向上
厚生労働省等の信頼できるデータ引用で情報の根拠を提示
要介護3の介護保険利用状況や給付内容は、厚生労働省及び各自治体の公式データに基づいています。公的な統計によれば、要介護3認定後の平均介護期間は約5〜6年とされており、月ごとの平均的なサービス利用内容や費用もこの範囲で策定されています。
下記テーブルで、要介護3に該当する際の主要な費用・制度を整理しています。
| 区分 | 支給限度額/月 | 自己負担割合 | 支援金等 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 介護サービス | 270,480円 | 1〜3割 | 対象外 | 超過分は全額自己負担 |
| デイサービス | 利用項目内 | 1〜3割 | 利用券など | 回数上限や内容ごとに要確認 |
| おむつ代 | 対象外(補助) | 有(申請) | 自治体助成 | 医師の証明や審査が必要な場合 |
| 補助金・給付金 | 個別申請 | 該当者のみ | 条件付き | 市区町村による要件の違い |
上記内容は公的情報及び自治体発表資料に基づいており、透明性と正確性を担保しています。
自治体ごとの給付金・助成の差異と最新情報紹介
要介護3でもらえるお金には自治体独自の助成や給付金があります。特に「おむつ代助成制度」や「紙おむつ給付」に代表される生活支援サービスは、各市区町村によって金額や申請条件、対象者が大きく異なります。
居住地域の福祉課や長寿介護課を通じて各種給付金の最新要件や申請方法を必ず事前に確認しましょう。
主な給付例
-
紙おむつ等の現物給付・助成制度
-
デイサービス利用料助成券
-
在宅介護者への負担軽減支援
-
医療費控除や確定申告上の控除申請
申請には医師の証明や要介護認定結果、所得確認書類などが求められるため、準備を計画的に進めることが大切です。地域によっては給付対象サービスや受付枠に上限があるため、最新情報を自治体窓口で確認し、適切な支援を受けることが重要です。
費用比較表と具体的シミュレーションによる見える化
要介護度別・サービス別の費用比較表の掲載
要介護3の方が利用する主な介護サービスや施設の費用について、要介護度ごとに比較できるように下記の表にまとめました。月額目安と自己負担割合、利用上限額も一目で把握できます。
| 要介護度 | 支給限度額(月) | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | 主な対象サービス |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 | 訪問介護、デイサービス |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 | デイサービス、リハビリ |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 | デイサービス、訪問介護、福祉用具 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 | 夜間対応、ショートステイ |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 | 特養入所、療養型施設 |
自己負担割合は、所得や収入に応じて決まっており、限度額を超えると全額自己負担となります。
特養費用シミュレーションやデイサービス利用料の具体例
要介護3の方が特別養護老人ホーム(特養)やデイサービスを利用する場合の月額費用をシミュレーションしました。施設やサービスごとの具体的な例を挙げることで、実際の負担をイメージしやすくしています。
| サービス/施設 | 利用頻度・目安 | 公的給付内の自己負担 | 公的給付外費用(食事・居住費等) | 合計月額目安 |
|---|---|---|---|---|
| 特養(多床室) | 入所 | 約27,000円(1割負担) | 約45,000〜70,000円 | 約72,000〜97,000円 |
| デイサービス | 週3回 | 約12,000〜18,000円 | 食費・おむつ代3,000〜6,000円 | 約15,000〜24,000円 |
| 訪問介護 | 週4回 | 約8,000〜15,000円 | ー | 約8,000〜15,000円 |
*食事代やおむつ代の負担は現金または実費精算となる場合が多いです。
*紙おむつ給付や助成制度も自治体によって用意されています。
利用者負担を抑える制度の組み合わせシミュレーション
費用負担を抑えるために活用できる各種制度や助成金を組み合わせることで、自己負担額を大幅に軽減できるケースもあります。
-
高額介護サービス費:自己負担上限を超えた分が払い戻される制度。月額上限は世帯や所得で異なります。
-
おむつ代助成:自治体の紙おむつ給付で月数千円〜1万円程度が補助される場合があります。
-
医療費控除:介護保険対象サービスやおむつ代の一部は確定申告で医療費控除の対象となります。
-
住宅のバリアフリー改修や福祉用具のレンタル・購入も、介護保険や自治体補助で多くがカバーされます。
主なポイント
- 所得区分や利用サービスによって自己負担や上限額が異なる。
- 公的制度・助成を活用し、ケアマネジャー等に相談しながら最適な組み合わせを検討することで、経済的負担の軽減が期待できます。
適切なサービス選択と助成制度の組み合わせにより、現実的な負担額や安心した生活設計が可能となります。
要介護3関連のよくある質問と疑問解消
もらえるお金はいくら?給付金の具体的数字と申請可能な制度
要介護3になると、直接現金でもらえるお金はありませんが、介護保険の支給限度額内でサービス費用の給付があります。要介護3の支給限度額は月約27万円(270,480円/2025年時点)です。この範囲内であれば各種サービス利用料の1~3割が自己負担となります。所得が一定以下なら、介護保険負担限度額認定証の利用でさらに負担が軽減される場合もあります。
| 項目 | 月額(上限) | 補足 |
|---|---|---|
| 介護保険支給限度額 | 270,480円 | サービス利用費用に対する給付 |
| 自己負担割合 | 1~3割 | 所得により変動 |
| 介護保険外の助成 | おむつ代など自治体による | 申請が必要 |
申請方法は市区町村へ要介護認定の申請後、認定通知を受けて各種制度へ申請します。
介護保険の自己負担割合と負担限度額に関する疑問
介護保険サービス利用時の自己負担割合は原則1割ですが、現役並み所得がある場合は2割または3割です。自己負担額は利用したサービス費用の合計額にこの割合をかけて計算します。支給限度額を超えると、超過分は全額自己負担となるため注意が必要です。
-
例:自己負担1割の場合
- 月のサービス利用額270,000円 → 負担27,000円
-
例:自己負担2割の場合
- 月のサービス利用額200,000円 → 負担40,000円
低所得者や高額介護サービス費の払い戻し制度もあるので、家計を守るためには制度の上手な活用が重要です。
デイサービスやおむつ代助成の申請方法と条件
デイサービスは要介護3の方が頻繁に利用する代表的なサービスです。料金はサービス内容と利用回数で異なります。月曜から金曜まで週5日利用する場合の目安は次の通りです。
| 利用回数 | 自己負担1割(月額目安) | 自己負担3割(月額目安) |
|---|---|---|
| 週3回 | 約15,000~19,000円 | 約45,000~57,000円 |
| 週5回 | 約25,000~32,000円 | 約75,000~96,000円 |
おむつ代に関しては介護保険では直接給付がありませんが、多くの自治体で助成制度が用意されています。申請には介護認定や医師の診断書などが必要です。控除が受けられるケースもあるので、申請前に市区町村の窓口やケアマネジャーへ相談しましょう。
一人暮らし・在宅介護は可能か?現状と支援策の紹介
要介護3でも一人暮らしで在宅生活を継続する方は一定数います。自宅での生活を維持するには、訪問介護やデイサービスなど多様な在宅サービスを組み合わせるケアプランが不可欠です。夜間の対応や急変時サポート、高齢者見守りサービスなどの利用も現実的なサポートとなります。
-
自宅生活を支える主なサービス
- 訪問介護:食事・入浴・排せつなどの日常生活支援
- デイサービス:日中の活動と食事・送迎
- 緊急通報装置:自治体による貸与事業など
一人暮らしが難しい場合には、短期入所(ショートステイ)や福祉用具のレンタル制度も活用できます。
施設入居時の費用負担と補助の違い
要介護3の方が特別養護老人ホームや有料老人ホームへ入所する際、サービス費用・食費・居住費などがかかります。介護保険からは介護サービス費用の補助が受けられますが、食費・居住費は原則自己負担です。所得や資産の状況で「負担限度額認定証」が交付されると自己負担額の軽減を受けられます。
| 施設費用 | 費用項目 | 支援制度・補助 |
|---|---|---|
| 介護サービス費 | 1~3割自己負担 | 介護保険で給付有 |
| 食費・居住費 | 実費(軽減あり) | 負担限度額認定制度 |
| その他費用 | おむつ代・日用品 | 一部自治体助成あり |
施設選びの前に、必要な支援や補助申請可能な条件をしっかり確認しておくことが重要です。