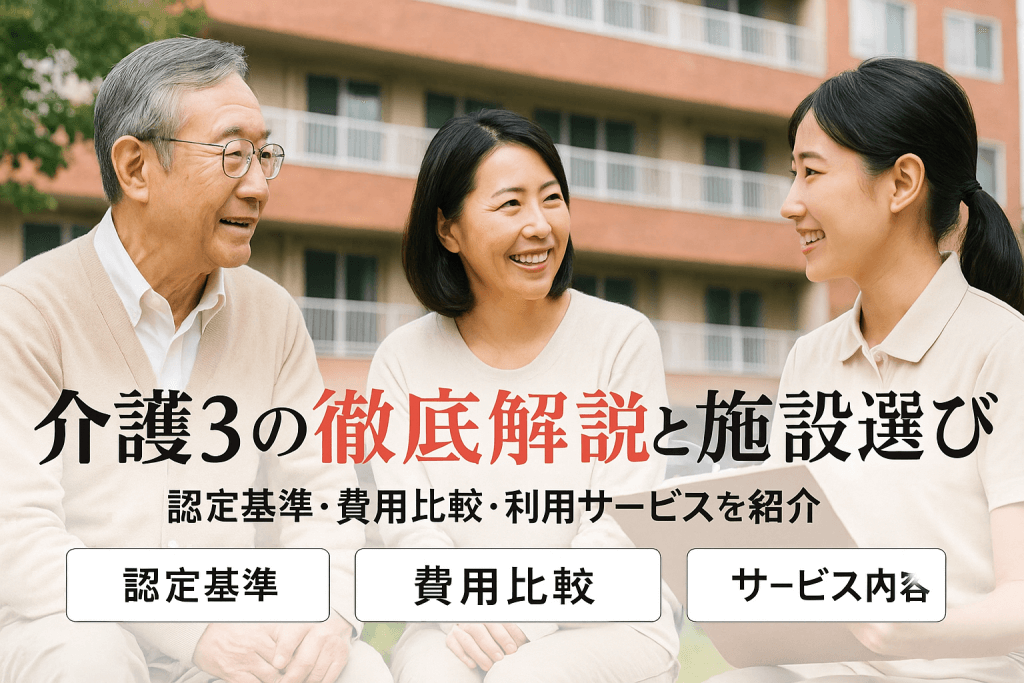「要介護3」と認定されたとき、「どれくらい生活に支障が出る?」「役所の支援や給付はどこまで受けられる?」「家族の介護負担や費用は?」と不安を感じていませんか?
要介護3は、【厚生労働省の審査基準】で「介護に必要な目安時間が1日70分以上90分未満」と定められています。歩行・立ち上がりに介助が必須となり、排泄や入浴はほぼ全面的な介助が必要です。認知機能の低下から、見当識障害・自己判断力の低下・問題行動も現れることがあります。
例えば、在宅で介護サービスを利用した場合、公的な支給限度額は【月々274,483円】(2024年度・全国一律基準額)で、原則1~3割の自己負担が生じます。さらに、認定によっては障害者控除や住宅改修補助の利用も可能となり、金銭面での備えや制度理解が生活の安心につながります。
「予想以上に費用がかかるのでは?」「どこまで自宅で介護できるのか?」とお悩みの方へ。本記事では、要介護3の具体的な状態や利用できるサポート、制度面の情報、比較できる介護度の違い、そして家族のためのリスク対策まで、専門家監修の情報をわかりやすくまとめています。
知らなかった制度や最適な選択肢で、少しでも負担や不安を減らせるヒントがきっと見つかります。ご自身やご家族の大切な時間、まずは正確な理解から始めてみませんか?
介護3とはどんな状態かを徹底解説!認定基準と身体・認知機能の特徴
要介護3の認定基準と介護時間の考え方
要介護3は、厚生労働省が定めた基準で「日常生活全般でほぼ全面的な介助が必要」と認定される状態です。認定基準時間は1日あたり70分以上90分未満の介護が必要とされています。介護度は、本人や家族の状況・生活環境まで考慮して審査されます。
下記テーブルは主な認定基準の違いをまとめたものです。
| 介護度 | 1日あたりの介護時間 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 要介護2 | 50~70分 | 部分的な介助が中心 |
| 要介護3 | 70~90分 | 全面的な介助が必要 |
| 要介護4 | 90~110分 | より長時間・専門的な介助が必要 |
要介護3では日常生活におけるほぼすべての面で介助が欠かせなくなります。
身体的な介護が必要な具体的動作例
要介護3の身体的特徴として、立ち上がりや歩行が自力では困難になり、ほぼ毎回介助を必要とするのが大きなポイントです。以下は、典型的な介助が必要な場面です。
-
歩行:杖や手すりがあっても自分だけでは歩けず、転倒リスクが高い
-
立ち上がり・着座:全介助を要する場合が多い
-
排泄:トイレまでの移動、おむつ交換、後始末まで全面的なサポートが必要
-
入浴:浴槽への出入り・身体の洗浄ともに介助無しでは危険
このような状況の場合、日常生活全般にわたってヘルパーや家族の継続的な手助けが求められます。一人暮らしの場合は、福祉用具や訪問介護サービスの積極的な活用が必要です。
認知症状の進行と行動面の特徴
要介護3では、認知機能が低下しているケースも多く見られます。主な認知症状や行動面の特徴は以下の通りです。
-
判断力の低下:日常の選択や行動が自分ひとりではできなくなる
-
時間や場所の認識障害:曜日や場所を間違う、帰宅願望が強まることもある
-
問題行動の発現:徘徊、物取られ妄想、不安定な気分などがみられやすい
この段階では、認知症ケアの専門知識を持つスタッフによる見守りやサポートが重要です。行動面の困難にも対応できるよう、ケアプランでは家族や介護事業者との丁寧な連携が求められます。人により進行度や症状は異なるため、状況に合った支援体制の構築がカギとなります。
介護3で受けられる公的制度・給付金・補助金の仕組みと目安
月額給付金や自己負担額の目安
要介護3に該当すると、介護保険から手厚い給付を受けられます。介護度ごとに支給限度額が定まっており、要介護3では月額約26万円程度が目安です。自己負担は原則1割ですが、所得によっては2割または3割となる場合があります。
以下の表で、主要介護度の支給限度額と自己負担額の一例を比較できます。
| 介護度 | 支給限度額(月額目安) | 自己負担(1割の場合) |
|---|---|---|
| 要介護2 | 約19.7万円 | 約1.9万円 |
| 要介護3 | 約26万円 | 約2.6万円 |
| 要介護4 | 約30万円 | 約3万円 |
自己負担を最小限に抑えるには、自治体やケアマネジャーに必要なサービスを相談しながら計画的に利用することが重要です。
障害者控除・税制優遇や介護リフォーム補助金
介護3に認定されている方は、税制面でも支援を受けられます。主な控除・補助制度としては以下のものがあります。
-
障害者控除:要介護3の認定を受けている方が特定条件を満たすと、所得税や住民税で障害者控除が適用されます。
-
医療費控除:介護サービス利用時の一部費用や介護リフォーム、福祉用具の購入費も医療費控除の対象となることがあります。
-
介護リフォーム補助金:手すり設置やバリアフリー改修など自宅介護を支える改修工事費を最大20万円まで補助する自治体もあります。
申請時には介護認定通知書や工事見積書などの提出が必要です。申請前に自治体福祉担当窓口や担当ケアマネジャーに必ず確認しましょう。
福祉用具レンタル・購入で利用可能な公的支援
要介護3では、福祉用具のレンタル・購入も公的支援の対象です。日常生活の自立支援や家族の負担軽減のため、幅広い品目が用意されています。
主なレンタル対象品目(一部)
-
車いす、車いす付属品
-
介護用ベッド
-
手すりや歩行器
-
スロープ、移動用リフト
購入補助の対象となる品目
-
ポータブルトイレ
-
入浴補助用具
-
使い捨ておむつ等
レンタル利用時は、ケアマネジャーに相談し、必要性を専門家と判断したうえで介護保険の申請を行います。購入補助の場合も、申請前に見積もりや必要書類の準備が欠かせません。介護用品店や地域包括支援センターを積極的に活用するとスムーズです。
介護3と他の介護度(2・4・5)の明確な違いと比較表
介護度は、日常生活にどれだけ支援や介助が必要かを示しています。特に介護3は、身体的・認知的な機能の低下が進み、日常の多くの場面で広範な介護が必要となります。下記の比較表では、要介護2・3・4・5の特徴や支援内容を一目で把握できるようにまとめています。
| 項目 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| 認定基準 | 一部の生活で介助が必要 | 多くの場面で全面的な介助が必要 | ほぼ全ての場面で全面的な介助が必要 | ほぼ常に全面的な介護と見守りが必要 |
| 身体機能 | 歩行や起き上がりは自力も可 | 歩行・起き上がり困難、自力移動は難しい | 寝たきりに近い、ほぼ自力での移動不可 | 固定ベッド上中心、体位変換も全面介助 |
| 認知機能 | 軽度または中等度の低下 | 認知症状が現れやすくなる | 認知症が進行、意思疎通も困難 | 重度の認知機能低下、意思疎通不可に近い |
| 主な支援内容 | 入浴・排泄・食事の部分的介助 | 入浴・排泄・食事など多くの動作で全面介助が必要 | 日常全般で介助が必要、見守りや医療的ケアも増加 | 24時間体制で全ての動作に介助が必要 |
| 施設入所目安 | グループホーム・サービス付き住宅等 | 特養・老健・有料老人ホームも選択肢になる | 特養など介護度が高い施設への入所が主 | 介護老人保健施設や医療機関での長期療養中心 |
要介護2と3の具体的違い
要介護2は、まだ自力で行える動作がいくつか残っており、軽い支援や部分的な介助を受けながら生活ができます。一方、要介護3になると、起き上がりや移動、日常の動作がほとんど自力では難しくなり、介護を受ける時間と範囲が大きく増加します。
-
要介護2の特徴
- 歩行や椅子への移動は部分的介助で対応可能
- 入浴や排泄、食事も自立部分がある
- 認知機能は軽度~中等度の低下が多い
-
要介護3の特徴
- 起き上がりや移動、歩行はほぼ全面的な介助が必要
- 認知機能がさらに低下し、介護者の見守りと積極的な支援が不可欠
- 多くの場合、24時間にわたりケアが必要な状態
要介護3・4・5の増加する介護度別の特徴と介護内容
要介護3から4、5へと介護度が進むにつれ、介護が必要な範囲や時間は格段に増加します。下記に特徴的なポイントを整理します。
-
要介護3
- 多くの基本動作で全面的な介助が必要
- 日中の見守りや頻繁な声掛け・対応が重要
- デイサービスやショートステイなども活用しやすい
-
要介護4
- ほぼすべての場面で全面的な介護が必要
- 体位変換、寝返りも自力では困難で、褥瘡予防管理も求められる
- 施設入所や医療的支援も検討されるケースが多い
-
要介護5
- 日常すべての動作に介助・見守りが不可欠
- 意思表示や食事も難しく、経管栄養など医療処置も含まれる
- 専門施設での24時間看護・介護体制が基本
これらの違いを理解することで、要介護3の方がどのような状態にあり、どんな介護やサービスが必要なのか、また今後の変化や施設選びの目安を知ることができます。ページで紹介した比較表やポイントを活用し、ご家族と相談しながら最適な介護環境を整える参考にしてください。
介護3で利用可能な介護サービスの種類と特徴
在宅で利用できる訪問介護・訪問看護サービス
在宅生活を支えるために、訪問介護と訪問看護はとても有効です。訪問介護は日常生活全般の支援や身体介助を中心に、訪問看護は健康管理や服薬管理、リハビリテーションなど医療的な側面に対応します。利用者の状態や希望により、必要なサービスの回数や内容が決まります。たとえば1日1〜2回の訪問や、週数回の利用が中心です。
主なサービス内容の比較表
| サービス名 | 主な内容 | 利用例 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 食事・入浴・排泄等の介助、掃除や洗濯 | 「着替え」「調理」「移動介助」 |
| 訪問看護 | 健康チェック、服薬管理、リハビリ | 「血圧測定」「創傷処置」「機能訓練」 |
利用には事前のケアプラン作成が必要です。家族の負担軽減や一人暮らしを継続するうえでも大きな役割を果たします。
通所介護・デイサービスの役割と活用法
デイサービスは、日帰りで施設に通い多様な支援を受けられるサービスです。利用者は入浴や食事、趣味・レクリエーションなどを通じて社会的な交流や活動の機会を得られます。送迎サービスも多くの施設で実施されているため、家族の負担を減らし、在宅介護の継続を助けます。
デイサービス活用のポイント
-
生活リズムの維持や心身機能の維持に役立つ
-
専門スタッフの目による見守りや介護方法のアドバイス
-
家族のレスパイト(休息)としても重要
利用回数やプログラム内容は個々のケアプランにより調整可能です。
短期入所(ショートステイ)と多様な宿泊型サービス
ショートステイは数日から数週間、介護施設に一時的に宿泊しながら介護と生活支援を受けられます。自宅介護を続けたいが、家族の休養や緊急時の預かりが必要な場合に便利です。サービス内容や受け入れ体制は施設で異なるため、事前に確認することが大切です。
ショートステイの主な特徴
-
家族が旅行や急用時に利用しやすい
-
リハビリや日常生活動作の維持を目的に利用可能
-
要介護度に応じて費用の自己負担額が異なる
宿泊型自宅サービスや小規模多機能型サービスなど、地域によって様々な形態が用意されています。
介護3対応可能な施設の種類と特徴(特養、老健、グループホーム等)
要介護3の方は以下のような多様な施設に入所できます。施設ごとにサービス内容や入所条件が異なるため、利用者や家族の希望に合わせて選択することが重要です。
主要な施設と特徴の比較表
| 施設名 | 特徴 | 入居条件 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 24時間介護、認知症対応、長期入居向き | 原則要介護3以上 |
| 介護老人保健施設 | 医療ケアやリハビリを重視、在宅復帰を目指す | 要介護1以上 |
| グループホーム | 少人数制で認知症の方向き、家庭的な雰囲気 | 認知症と診断・要支援2以上 |
施設選びでは、利用者の身体状況や認知症の有無、希望する生活スタイルなどに応じて比較検討することが大切です。各施設とも見学や相談を利用し、納得のいくサービス選びを進めましょう。
介護3でのケアプラン作成の実例と費用シミュレーション
家族同居時のケアプランと介護費用構成
要介護3では、家族の助けを得ながらも日常生活動作の多くで専門的な支援が必要となるため、在宅サービスの活用が重要です。主なサービスとしては、訪問介護、デイサービス、福祉用具レンタルなどが組み合わさります。
以下のテーブルは、代表的なサービスと平均的な自己負担額(1割負担の場合の目安)を示しています。
| サービス名 | 利用頻度例 | 月額自己負担(円) |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 週5回 | 9,000 |
| デイサービス | 週2回 | 7,000 |
| 福祉用具レンタル | 常時 | 1,500 |
| 訪問看護 | 週1回 | 2,000 |
| 合計 | ― | 19,500 |
家族同居でも、日中の家族不在や夜間の見守りが課題になる場合はホームヘルパーの利用が増加します。また、必要に応じて短期入所(ショートステイ)を活用することで家族の負担軽減も可能です。
一人暮らし高齢者向けケアプランの工夫と課題
一人暮らしの高齢者が要介護3の場合、事故や健康悪化のリスクが高まるため見守りサービスや緊急時対応が不可欠となります。多くのケースで機器を利用した安否確認や、地域巡回型の見守りサービスを組み合わせたケアプラン設計が行われています。
工夫の一例として、
-
毎日の訪問介護による生活支援と身体介護
-
緊急通報装置やセンサーマットによる安否確認
-
郵便物・新聞の配達確認も含めた地域連携
などが挙げられます。
また、定期的なショートステイやデイサービスの組み合わせにより、高齢者の生活リズム維持と家族の精神的負担を軽減できます。しかし、独居高齢者の場合、介護サービス利用の限度額内におさえる工夫や、費用負担の調整が大きな課題となります。
施設入居時の費用とサービス利用の実態
要介護3の方が介護施設(特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホームなど)を利用する場合、本人の状態に合わせて手厚い介助を受けられます。施設の種類とサービス内容により費用には幅がありますが、主な内訳は以下の通りです。
| 費用項目 | 月額目安(円) |
|---|---|
| 入居一時金 | 0~数百万 |
| 基本利用料金 | 80,000~150,000 |
| 介護サービス費用 | 30,000~60,000 |
| 食費・生活費 | 30,000~60,000 |
| おむつ代・医療費等 | 5,000~15,000 |
施設入居の場合、日常生活全般にわたり24時間体制で介護が受けられるのが大きな強みです。一方、入居時の初期費用や月額負担が高くなるため、自治体制度や給付金の活用、入居前の費用詳細の確認が重要です。経済的な負担やケア内容ごとの比較を事前に丁寧に進めることをおすすめします。
介護3と認知症ケアの現状と課題、家族が直面する生活リスク
認知症の進行に伴う行動変化と対応策
認知症が進行すると、本人の生活動作や行動にさまざまな変化が現れます。特に行動・心理症状(BPSD)は家族や介護者に大きな負担となりやすく、早期の対応が求められます。
主なBPSDの例
-
徘徊や帰宅願望
-
急な怒りや不安の訴え
-
食事拒否
-
もの取られ妄想
これらに対しては、本人の生活リズムを整え、安心できる環境を作ることが効果的です。また、地域包括支援センターやケアマネジャーとの連携で、デイサービスや訪問介護など外部のサービスを積極的に活用する対策が重要となります。
BPSDの主な対応策一覧
| 行動・症状 | 対応策例 |
|---|---|
| 徘徊 | 玄関の施錠強化、GPS付き見守り機器利用 |
| 怒り・不安 | 本人の気持ちに寄り添い、安心できる声かけや環境調整 |
| 食事拒否 | 好みの食事を用意、楽しい雰囲気で一緒に食事 |
| もの取られ妄想 | 決して否定せず、安心できる説明と対応が大切 |
介護者の身体的・精神的負担の実態と支援策
介護3の状態になると、着替えや排泄、食事介助などの支援が毎日必要になります。これに伴い介護者には身体的・精神的な負担が増え、ストレスや体力の消耗、時には燃え尽き症候群につながることもあります。
負担軽減のための支援策
-
介護サービスの利用
訪問介護やデイサービス、高齢者短期入所施設(ショートステイ)などを定期的に利用し、家族の休息時間を作ることが重要です。 -
相談窓口の活用
地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、公的支援や介護用品レンタル制度を利用することで負担を軽減できます。 -
家族間の分担や周囲の協力
家族や近親者同士で役割分担し、孤立を避けましょう。
家族介護の負担軽減チェックリスト
-
訪問介護やデイサービスの導入
-
ショートステイの活用
-
介護用品や福祉用具のレンタル
-
周囲への相談と協力体制構築
家族介護で予想される経済的リスクと備えのポイント
介護3の状態になると、介護サービス利用や福祉用具の購入、住宅改修費、施設入居準備などさまざまな出費が想定されます。経済面の負担を軽減し、安心して介護生活を続けるためには事前の準備と公的制度の理解が欠かせません。
主な費用負担例
| 項目 | 月額の目安 | 対応策 |
|---|---|---|
| 自宅介護 | 3万~5万円 | 介護保険サービス利用で自己負担割合軽減 |
| 施設入居 | 15万~30万円 | 施設ごとの料金体系や負担割合を比較検討 |
| 介護用品購入 | 数千円~ | レンタル制度、医療控除の活用 |
備えのポイント
-
介護保険や高額介護サービス費制度を最大限活用し、負担額を抑える
-
住宅改修や福祉用具の購入には公的補助を利用
-
事前にケアマネジャーへ相談して最適なケアプランを設計
このように、専門サービスや公的支援を活用し、家族と本人双方が安心できる介護環境を整えることが大切です。
介護3で選びたい施設・サービス選びのポイントと申込みの流れ
サービス・施設の比較検討基準
介護3の方が利用する施設・サービスを選ぶ際には、医療体制や居住環境、費用面を総合的に検討することが重要です。以下の比較表で主な選択肢と特徴を整理します。
| 種類 | 医療支援 | 居住環境 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 24時間体制看護対応 | 個室・多床室あり | 月10~15万円前後 |
| 介護付き有料老人ホーム | 看護師常駐/医療連携 | 個室・設備充実 | 月15~30万円以上 |
| グループホーム | 認知症専門医療連携あり | 少人数制・家庭的 | 月13~20万円前後 |
| 在宅サービス | 訪問看護/リハビリ対応 | 自宅環境を活かせる | サービスにより変動 |
サービスの選定時は、要介護3の方の状態や家族構成、認知症の有無、日常生活で必要な介助内容も考慮しましょう。特に医療ニーズが高い場合は医療・看護体制が整った施設が適しています。費用は自己負担となる部分もあるため、必ず事前に確認し計画的に選ぶことがポイントです。
申込み・見学時のチェックリスト
施設申込みや見学時に押さえておきたい重要項目をチェックリスト形式でまとめます。
-
医療・看護体制の有無
-
介護スタッフの人数と質
-
部屋の清潔さと居住空間
-
食事や入浴のケア内容
-
夜間や緊急時の対応体制
-
施設見学時の雰囲気や対応
-
利用料金の詳細や追加費用
-
家族の面会・サポート体制
-
退居や変更時の規定
これらは、ご本人と家族が安心して生活できるかどうかを見極める上で欠かせないポイントです。見学は複数施設を回り、実際の雰囲気や生活イメージをしっかり確認しましょう。スタッフや入居者の様子、コミュニケーションが円滑かどうかも大きな判断材料となります。
介護保険申請から認定までの具体的流れと注意点
介護3の認定を受けるためには、介護保険の申請から認定まで複数のステップがあります。主な流れは下記の通りです。
- 市区町村の窓口で申請書を提出
- 主治医の意見書を準備
- 訪問調査による本人・家族への聞き取り
- 認定審査会による総合判定
- 介護度の通知(認定)
申請時の書類作成や調査では、普段の生活で介助が必要な場面を正確に伝えることが重要です。要介護3と判断されるには、日常生活全般で相当な介助が必要な実情を具体的に説明しましょう。認定後はケアマネジャーと相談し最適なケアプランを作成し、サービスや施設利用の準備を進めてください。上手に進めることで、適切なサポートや費用補助が受けやすくなります。
介護3に関するQ&A~読者の疑問を幅広く丁寧に解決
Q1 要介護3でもらえるお金の目安は?
要介護3では、介護保険を利用して受け取ることのできる給付額の上限が定められています。月額の支給限度額は約26万円前後(2025年現在)で、利用者負担は原則1割、収入状況により2割または3割です。自己負担分を差し引いた金額が実際のもらえるお金の目安となります。具体的な額は利用サービスの内容や回数によっても異なるため、ケアマネジャーや市区町村の窓口で確認しましょう。
| 要介護度 | 月額支給限度額(目安) | 自己負担割合(原則) |
|---|---|---|
| 要介護3 | 約26万円 | 1~3割 |
Q2 介護2と3の違いは具体的に何ですか?
要介護2と3の違いは、日常生活の自立度や介助の必要範囲にあります。要介護2は部分的・一部の動作のみ介助が必要ですが、要介護3はほぼ全般的な動作で介護が必要です。具体的には、歩行や立ち上がり、衣服の着脱、入浴やトイレ動作も他人の助けなしでは難しくなります。判定基準も重度化し、認定の際は介護される時間や認知症状の有無も加味されます。
-
要介護2:一部介助・自立支援の余地あり
-
要介護3:全面的・連続的な介助が必要
Q3 要介護3は自宅介護で可能ですか?
自宅介護は可能ですが、介護3の方には介護サービスの積極的な利用が必須です。定期訪問介護やデイサービス、夜間サポートなどを組み合わせて介護負担を分散する必要があります。ご家族だけでの介護は心身ともに大きな負担となるため、福祉用具や住宅改修の活用も視野に入れましょう。医療的ケアが必要な場合は訪問看護の利用もおすすめです。
-
介護サービスの併用が前提
-
家庭ごとの支援体制構築が重要
Q4 どのような施設が要介護3に適していますか?
要介護3の方が利用しやすい施設には、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホームなどがあります。各施設の特徴を把握し、本人の状態や希望に合わせた選択が大切です。
| 施設名 | 特徴 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 介護度3以上が基本入居条件、長期入所可 |
| 介護老人保健施設 | 医療的ケアとリハビリに強み、在宅復帰を目指す |
| 有料老人ホーム | 生活支援や介護サービス充実、民間運営で選択肢が広い |
| グループホーム | 少人数制で家庭的な環境、認知症対応型が中心 |
Q5 認知症がある要介護3の介護で注意すべき点は?
認知症がある場合、徘徊や転倒予防、安全対策が不可欠です。環境整備や声かけの工夫、定期的な見守りが安全確保には重要です。ストレスをためないよう、本人のペースに合わせて接することも配慮しましょう。介護者同士の連携と、専門職による相談体制構築も有効です。
-
環境の安全対策
-
コミュニケーションの工夫
-
見守りと適度な刺激のバランス
Q6 介護3の利用できるデイサービスの内容と料金は?
要介護3の場合、デイサービスでの入浴介助、食事、リハビリテーション、レクリエーション活動など多様なサービスを利用できます。1回あたりの料金は自己負担割合で異なりますが、送迎や日常生活介助が含まれており、1〜2千円程度が目安です。加算や特別サービスがある場合は料金が変動しますので、事業所ごとに詳細確認が必要です。
-
入浴・食事・機能訓練
-
送迎付き
-
料金: 1回あたり1,000〜2,000円目安
Q7 補助金や控除の申請で気をつけることは?
補助金や控除申請には正確な書類準備が必要です。介護認定通知、医師の診断書、サービス利用証明などを整えましょう。また、申請期限や必要項目の記載ミスには注意してください。自治体や年金事務所、税務署に早めに相談して、抜け漏れなく手続きを進めることが大切です。
-
書類の漏れ・誤記防止
-
申請窓口・必要書類の事前確認
-
早めの準備
Q8 一人暮らしの要介護3が利用できる支援サービスは?
要介護3で一人暮らしの場合、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、緊急通報システム、配食サービスなど多様な支援策が利用可能です。ケアマネジャーと相談し、生活全般をカバーするサービスを個別に組み立てましょう。地域包括支援センターの活用もポイントです。
-
訪問介護
-
緊急通報・見守り
-
配食・移動支援
Q9 介護3の状態での福祉用具レンタルについて
要介護3で利用可能な福祉用具には、ベッド、手すり、歩行器、車いす、介護用トイレなどがあります。申請は介護保険を通じて行い、自己負担は原則1割からです。ケアマネジャーへの相談で本人の状態に合った用具を提案してもらえます。必要に応じて住宅改修費用の助成も利用できます。
| 主な福祉用具 | レンタル対象 |
|---|---|
| 介護ベッド | ○ |
| 手すり | ○ |
| 車いす | ○ |
| 歩行器 | ○ |
| 介護用ポータブルトイレ | ○ |