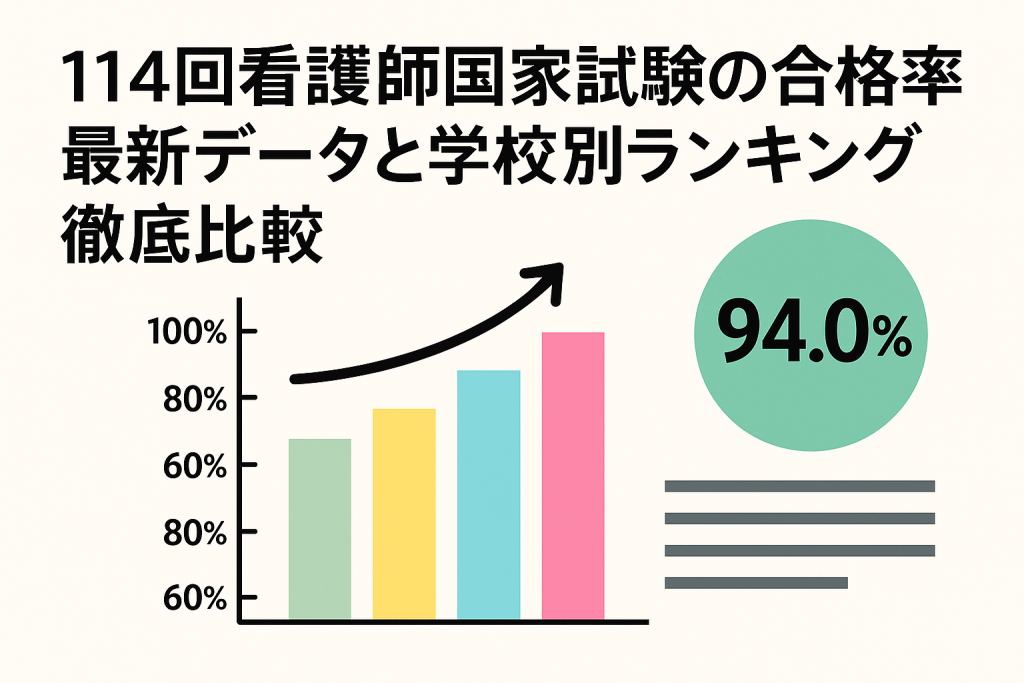「第114回看護師国家試験の合格率は【90.8%】。厚生労働省が正式に発表したこの数字は、全国6万5千人以上が受験した中で約5万9千人が合格したことを意味します。合格率だけでなく、新卒と既卒の差・学校ごとの実績・都道府県別の傾向も明らかになっています。
「今回、想定外の難問や採点除外問題が発表され、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。『自分の得点がボーダーラインに届くのか』『どの学校なら合格しやすいのか』と悩む受験生や再挑戦を目指す皆さんのために、数字や事例から現状を徹底的に解説します。
読み進めるほど、合格に近づくための“本当に必要な情報”が明確になるはずです。今の自分に必要なヒントを見逃さず行動に移したい方は、ぜひこのまま続きをご覧ください。
第114回看護師国家試験における合格率の最新データと全体傾向
114回看護師国家試験における合格率の公式数値と過去5年の推移
第114回看護師国家試験の合格率は90.1%(合格者数56,906人/受験者数63,131人)でした。近年の合格率推移をまとめると、いずれも80%後半から90%前半を維持し、安定して高水準で推移しています。
| 回数 | 合格率 | 合格者数 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 110回 | 89.1% | 58,684 | 65,569 |
| 111回 | 90.7% | 59,425 | 65,569 |
| 112回 | 91.0% | 59,766 | 65,567 |
| 113回 | 89.3% | 58,514 | 65,484 |
| 114回 | 90.1% | 56,906 | 63,131 |
このように、合格率は大きく変動せず、看護師の国家試験は合格しやすい資格試験のひとつと評価されています。
厚生労働省が公表する合格率データ詳細(90.1%の内訳と比較)
合格率90.1%の内訳は、大学卒・専門学校卒・既卒など幅広い受験者で構成されています。特に大学新卒は約96%という高い合格率を維持しており、専門学校新卒でも約89%と高率です。既卒者・再受験者は70%台半ば~80%前半になる傾向が見受けられます。
| 区分 | 合格率 |
|---|---|
| 大学新卒 | 96% |
| 専門学校新卒 | 89% |
| 既卒 | 75-82% |
新卒は全体を押し上げており、教育機関の指導力の高さが反映されています。
新卒・既卒別合格率の違いとその背景
新卒と既卒で合格率に明確な差があるのは、出題傾向や法制度の改定に最新で慣れているかどうか、また受験勉強のブランクがあるかが大きな要因です。新卒は学校側で模擬試験や演習対策が徹底されているため、知識の新しさと演習実績が合格率向上を支えています。既卒者の場合、独自での学び直しや情報収集力が重要になり、不利になりやすい傾向です。
合格率が示す試験の難易度と今年の傾向分析
第114回も例年と同様に難易度は標準的とされており、必修問題・一般問題・状況設定問題の配分に大きな変更はありません。そのため、基礎学力と過去問演習に注力した受験生が安定して合格を達成しています。
特徴的なのは、試験範囲の広さと実践的な設問が多い点です。十分な準備と最新の傾向把握が対策の要であり、合格率の高さは適切な学習法・受験対策が浸透している証でもあります。落ちる人の特徴として、苦手分野を放置したまま本番を迎えるケースが多く見受けられます。
令和時代の合格率変動パターンとその原因解説
令和時代以降、合格率はおおむね安定し、受験者数に多少変動はあるものの、難化傾向は限定的です。これは厚生労働省による試験内容のバランス見直しや、教育現場での国家試験対策強化が要因です。また、過去の「難しかった年」も記憶に新しいですが、最近は例年80~90%台の高水準となっています。難易度が急激に上がる心配は当面ないと考えられます。
採点除外問題が存在した場合の合格率への影響
国家試験では一部設問で採点除外問題や配点修正が生じた場合、全体の合格率にわずかに影響する場合があります。ただし、受験者の得点バランスが保たれるよう取り扱われるため、合格ラインやボーダーが極端に変動することはほとんどありません。これにより受験者ごとに大きな不利益が出ることは原則なく、安定した合格発表が行われています。
学校別・専門学校別で見る114回看護師国家試験における合格率ランキングと教育実態
114回学校別合格率ランキング発表!大学・専門学校の違いを比較
第114回看護師国家試験の合格率は全国平均で90.1%となりましたが、学校別に見るとその差は明確です。特に多くの大学や一部専門学校で合格率100%が確認されており、教育内容や指導体制の違いが合格結果に現れています。
下記のテーブルは主な大学・専門学校の合格率を一覧化したものです。
| 学校名 | 合格率 | 合格者数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 順天堂大学医療看護学部 | 100% | 195 | 手厚い国家試験対策 |
| 藤田医科大学保健衛生学部 | 100% | 103 | 実践的教育カリキュラム |
| 防衛医科大学校 | 100% | 102 | 厳格な教育指導 |
| 専門学校A | 98.5% | 100 | 模擬試験充実・現場実習重視 |
合格率100%達成校は教育方針が明確で、国家試験直前のサポートや実務に直結する授業が充実しています。
合格率100%を達成した学校の特徴と教育内容の考察
合格率100%を達成した学校には以下の共通点があります。
- 徹底した国家試験対策プログラムの導入
- 個別指導やチューター制度の充実
- 実習と座学のバランスに優れたカリキュラム
- 模擬試験や過去問題演習の定期実施
これらの学校は国家試験だけでなく、現場で活躍できる看護師の育成にも力を入れています。学生一人ひとりへの細やかなフォローやグループ学習の積極活用が高い合格率へと直結しています。
学校別合格率変動の要因分析と最新トレンド
合格率の変動にはいくつかの要因が関係しています。
- 新設校や定員増による指導体制の変化
- 入学者偏差値や学習意欲の違い
- 模擬試験の質や受験直前のサポートの手厚さ
- 現場実習と連携した教育の有無
近年では、AIやICTを活用したオンライン学習、ピアサポート、学校独自のサポートプログラム導入が増加し、合格率向上に貢献しています。これにより、従来よりも教育格差の是正が図られています。
専門学校別合格率の推移と大学との比較ポイント
専門学校と大学の合格率を比較すると、大学が高水準を維持する一方で、専門学校の合格率はやや幅があります。全国の専門学校でも90%超が主流ですが、進学先選びにおいては指導体制や先輩合格実績も重要です。
| 種別 | 全国平均合格率 | 合格率上位校 | 合格率下位校 |
|---|---|---|---|
| 大学 | 95%以上が主流 | 100%(複数校) | 90%前後 |
| 専門学校 | 90%前後~98% | 100%(一部校) | 80%台も存在 |
大学は全体的に安定した合格率を示す一方、専門学校は学校ごとの差が大きいのが特徴といえます。
近年の動向から読み解く専門学校の強みと課題
専門学校は、実践的カリキュラムや現場経験を重視するため、即戦力となる看護師の養成に優れています。
- 現場と連携した実習プログラム
- きめ細かい進路相談・就職指導
- 地元医療機関との深いパイプ
その一方で、合格率が伸びない学校では学生サポートや模擬試験制度の未整備が課題です。今後は、他校の好事例を参考に、教育水準向上への取り組みが重要となります。
強みを生かしながら、さらなる教育改善を図ることで、より多くの合格者輩出が期待されています。
合格基準・ボーダーラインの詳細と114回における合格に必要な得点構成
第114回看護師国家試験では、多くの受験生が気にする合格基準とボーダーラインは、厚生労働省が定めた規定に基づいて決まっています。合格のためには、必修問題・一般問題・状況設定問題それぞれで基準点を満たす必要があります。特に必修問題は正答率80%以上が求められるため、ここでのミスが致命的になることもあります。状況設定問題では臨床状況を的確に判断する力が必要です。これらの配点と合格基準を把握することが、国家試験合格の重要なポイントとなります。さらに、今回から一部出題形式や問題配分が見直された点も受験戦略に影響します。
必修問題・一般問題・状況設定問題別の配点と合格基準
看護師国家試験は大きく三種類の問題で構成されています。
| 問題区分 | 問題数 | 配点 | 合格基準 |
|---|---|---|---|
| 必修問題 | 50問 | 1問1点 | 80%(40点以上) |
| 一般問題 | 177問 | 1問1点 | 総得点の約60%(107点以上目安) |
| 状況設定問題 | 53問 | 1問2点 | 含めて計算・合格点に必要 |
必修問題で一点でも多く得点し、一般・状況設定問題で総合点を稼ぐ戦略が有効です。配点のバランスを知ることで優先度高く対策可能となります。
ボーダーライン決定の仕組みと114回の具体的数値
ボーダーラインは毎年受験者全体の学力にあわせて決められます。第114回では、必修問題は「40点以上」、一般+状況設定問題の合計で「162点以上」がおおよその目安となりました。合格基準点は「問題の難易度」や「全体平均点」を踏まえ厚生労働省が決定します。これにより公平性が担保され、年ごとの試験の難易度変化にも柔軟に対応しています。学校別や専門学校ごとの合格率もこのボーダーに沿って算出され、公表されています。
過去のボーダーライン変動から読み解く合格の難易度
過去数年のボーダーラインを見ると、毎年60%前後で大きな変動はありませんが、問題の難しさや受験者層により微妙な増減があります。難しかった年や易しかった年は、実際の平均点や合格率に反映されやすいのが特徴です。直近3年を比較すると、以下の通り推移しています。
| 年度 | 必修ボーダー | 一般+状況設定ボーダー | 全国合格率 |
|---|---|---|---|
| 112回 | 40点 | 158点 | 91.3% |
| 113回 | 40点 | 161点 | 89.5% |
| 114回 | 40点 | 162点 | 90.1% |
このように、おおよそ同じ基準ですが、年度ごとの微調整も見られます。学校別ランキングでは例年、国公立・一部私立大学や専門学校の合格率が100%となることもあり、教育水準の高さと直結しています。
ボーダー点数と合格率の相関分析
ボーダー点数が高いと一般的には合格率が下がる傾向ですが、看護師国家試験は合格率が安定して高く推移する特徴があります。その理由として、教育機関の指導体制強化と受験生全体のレベルアップが挙げられます。また、厚生労働省の合格率やボーダー設定の公平性により、毎年安定した結果になっています。とくに合格率上位の学校では、学内模試・国家試験対策講座を重視し、一定水準以上の学力維持を実現しています。これにより看護師国家試験の全体的な難易度は維持されつつ、高い合格率が続く状況となっています。
114回看護師国家試験の難易度と合格率に影響を与えた要因
114回試験の難易度評価と受験生のリアルな反応
114回看護師国家試験は例年と比較して大きな難易度の変動はなく、過去の試験と同程度の出題傾向とされています。受験生からは「一部問題が難しい」「一般問題の一部が予想外だった」という声も挙がりましたが、全体的には合格を十分に狙える内容と評価する参加者が多くいました。実際に合格率は90.1%と高く、学校別ランキングでも大学・専門学校問わず合格率100%を達成する教育機関が複数見られました。
受験生の声としては、以下の点が多く挙がっています。
- 基礎問題が多く、標準的な対策で対応可能だった
- 新しい臨床知識や制度改革に関する出題が強化された
- 難問や時間のかかる問題が数問あった
高い合格率を支えるポイントは、最新の傾向を反映した学習と、過去問題の徹底的な演習にあったといえます。
試験問題の傾向および難問例の紹介
114回試験の問題傾向は以下の通りです。
| 問題分野 | 主な特徴 |
|---|---|
| 基礎知識 | 医療制度や看護技術など基礎力を問う出題 |
| 応用力 | 症例ごとの対処や倫理的視点を問う応用型問題 |
| 最新動向 | 新型感染症対策やICT活用など時事関連の問 |
特に応用力を問うケーススタディ形式が増加し、状況把握や臨床判断に関する難度の高い設問が含まれました。具体的な難問例としては「複雑な症例の対応」「多職種連携による判断」「難解な法規や制度改正」の出題が受験生の壁になりやすい傾向です。
採点除外問題の有無とその試験への影響
114回試験では一部問題において採点除外が発生しました。これらは設問自体の不備が指摘されたケースで、厚生労働省が公表した内容に基づき該当する設問は原則として合否への影響がないよう配慮されています。
採点除外の詳細と影響のまとめ:
- 多くの場合、受験生の得点に影響しないよう除外措置が取られる
- 該当する問題が合否を左右する場面はきわめて限定的
- 採点除外数の増減が毎年の合格率への直接的影響は小さい
安心して正当な評価が得られる採点体制が維持されています。
問題の難易度変動が合格率に及ぼす影響分析
問題難易度の増減は学校ごとの合格率ランキングや全体の合格率に直結します。特に114回のように難問があっても、基礎的な設問が多ければ受験生全体の得点率は安定します。
| 年度 | 合格率(全体) | 新卒合格率 | 主な傾向 |
|---|---|---|---|
| 113 | 89.3% | 95% | 難易度やや高め |
| 114 | 90.1% | 95.9% | 難易度標準 |
難易度が大きく上昇する年には合格基準点(ボーダー)が調整されることもあり、毎年安定した合格率となるよう設計されています。
基礎問題を確実に押さえることで、合格を目指す受験生が有利になる構造は今後も変わりません。各学校・専門学校別の合格率チェックや、厚生労働省発表のデータ活用が有効です。
新卒・既卒・再受験生別の合格率の違いとその理由
第114回看護師国家試験では、受験者の属性によって合格率に明確な差が見られます。新卒者は合格率90%超、既卒者や再受験者はそれより低くなる傾向があります。これは学習環境や受験動機、準備期間の違いが大きく影響します。下記のテーブルで各層の合格率の比較を示します。
| 区分 | 合格率 | 備考 |
|---|---|---|
| 新卒 | 約95% | 学校別で100%多数 |
| 既卒 | 約60-70% | 合格率低め |
| 再受験生 | 約50-65% | 個人差が大きい |
この違いは、卒業直後の新卒が知識を保持したまま受験すること、既卒・再受験生は期間が空いている分、最新の試験傾向への順応が難しい点が大きいです。また、合格率の高い学校や専門学校の選択も、結果に直接関与しています。
新卒者が高い合格率を維持する要因
新卒者が高い合格率を維持できる理由は以下の点にあります。
- 直前まで学校で専門的な教育を受けている
- 過去問題演習や直前模試による試験対策が充実している
- 指導体制が整った学校や合格率100%を達成する専門学校が存在する
- 同期や仲間と学ぶことでモチベーションを維持しやすい
一般的に新卒者は問題傾向や最新の出題範囲を把握しており、受験勉強のリズムを崩さずに試験へ臨むことができます。特に合格率が高い大学や専門学校は、国家試験対策プログラムに力を入れている傾向が強いです。
学習環境や受験動機の違いによる影響
新卒者と既卒・再受験生の間で、学習環境や受験動機には次のような違いがあります。
- 学習環境の違い 新卒者は学校や指導教員の支援を受けやすく、グループ学習や共同演習など、効率よく情報を得やすい状況です。これに対し既卒・再受験生は独学に頼る傾向が強くなります。
- 受験動機の違い 新卒者は「早期合格・就職」という明確な動機に支えられて努力するケースが多い一方、既卒・再受験生は再チャレンジへの不安やプレッシャーが強くなりがちです。
この違いは学習効率や精神的安定にも影響し、結果として新卒者の方が安定して高い合格率となります。
既卒者・再受験者の合格率と課題点
既卒者や再受験生の合格率は新卒者より低く、約60~70%となっています。その背景には、下記の課題があります。
- 試験範囲の最新傾向へのキャッチアップが遅れる
- 学習ペースが自己管理となり、モチベーション維持が難しくなる
- 指導やサポートが受けにくく、不安を感じやすい
特に厚生労働省発表の学校別合格率でも、既卒・再受験生が多い専門学校は合格率が安定しない傾向が見られます。
複数回不合格者の特徴と効果的な再挑戦法
複数回受験しても合格できなかった場合、共通して以下の特徴が見られます。
- 試験勉強の進め方が非効率(計画性がない、過去問演習不足)
- 苦手分野を放置してしまう
- メンタル面での動揺や自己管理の難しさ
再挑戦する場合の効果的な方法は以下の通りです。
- 課題分析
自分が苦手な分野や失点しやすい問題を洗い出し、その克服に集中する - 学習計画の再構築
具体的なスケジュールを作成し、毎日決めた時間の勉強を継続 - 模擬試験や予備校活用
模試を定期的に受けて現状を把握し、必要なら学校や予備校・通信講座など外部サポートを活用 - メンタルケア
ストレス解消やポジティブな自己暗示を取り入れて自信を高める
これらを組み合わせることで、再受験者でも合格率向上が期待できます。
不合格者の傾向分析と合格のための対策ポイント
不合格者の点数分布と具体的な失点原因
不合格者の多くは合格基準ギリギリで惜しくも届かないケースが目立ちます。114回看護師国家試験では、必修問題・一般問題ともに高得点層と低得点層に分かれる傾向がありました。特に必修問題の失点は致命的で、知識の抜けやケアレスミスが目立ちます。また、一般問題では一部の分野に偏った学習により失点するケースが多いです。
| 主な失点原因 | 詳細 |
|---|---|
| 必修問題の基礎力不足 | 看護理論や倫理の用語での取りこぼし |
| 一般問題の分野対策不足 | 小児看護、精神看護など出題範囲の偏り |
| 時間配分ミス | 焦りによる選択肢の読み落とし |
| 過去問対策の不十分 | 出題パターンの理解不足 |
幅広い範囲の知識定着とミスの自己分析が合格への第一歩となります。
必修問題の落とし穴と一般問題の攻略法
必修問題は出題数が少なくとも配点が高いため、1問の失点が大きな影響を及ぼします。難易度自体は高くありませんが、過信による見落としや基本用語の確認漏れが落とし穴です。日々の復習と端的な解答練習が有効です。
一般問題では、頻出テーマに絞った重点学習が合格率向上の鍵です。全体を俯瞰しつつも、「事例問題」「状況設定問題」などケースごとの攻略を積み重ねることが重要です。模擬試験に取り組み、間違えやすい設問はノートにまとめて反復することが失点防止につながります。
再受験に向けた効果的な学習法と精神的ケア
再受験生にとっては、前回の自分の弱点を分析した上で新たな学習計画を立て直すことが重要です。過去問や模試、学習記録を用い、頻出分野を中心に知識の穴を埋めます。
再チャレンジ時の主な学習法は以下の通りです。
- 強化すべき分野を可視化し、毎日の学習スケジュールを作成
- 苦手な出題形式へ重点的に取り組む
- オンライン学習やグループ学習で相互指導を活用
- 問題ごとに「なぜ間違えたか」の記録を残す
不安やプレッシャーへの対策には、適度な休息や合格体験談の活用、サポート体制のある環境作りが欠かせません。
長期受験生の成功例と持続的な対策法
長期間にわたり受験を続けている方の中にも、最終的に合格を勝ち取った事例が多数あります。成功者の多くは、継続的な習慣化と生活リズムの見直し、そして模試や過去問による弱点管理を徹底しています。
長期受験生におすすめの実践法は以下です。
- 1日30分からの積み重ねで無理なく継続
- 合格率が高い学校や予備校の情報を積極的に収集
- 精神的な負担軽減のための相談相手やカウンセリング活用
- 合格目標日を定めて明確なロードマップを作成
自身のペースを大切にしながらも、時には新たな学習法やツールを取り入れる柔軟性が、合格への近道となっています。
地域別・都道府県別の合格率の差とその背景
都道府県別合格率ランキングと地域差の現状
看護師国家試験の合格率は、都道府県ごとに明確な差が見られます。これは各地域の教育体制や学校ごとの支援制度の違いが影響しているためです。最新の合格率データをもとに、都道府県ごとの上位と下位のランキングを以下のテーブルで示します。
| 都道府県 | 合格率(%) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 東京 | 96.2 | 大規模大学・専門学校集中 |
| 京都 | 95.8 | 伝統的な看護教育機関の充実 |
| 福井 | 95.3 | 少人数指導・高い定着率 |
| 沖縄 | 91.0 | 地域医療重視の独自教育が特色 |
| 青森 | 88.7 | 地域偏在・受験者数が少ない |
| 秋田 | 88.1 | 少子化・校数少、ばらつきあり |
このように地域差は明確で、都市部や歴史ある教育機関が多い都道府県では、合格率が全国平均を上回る傾向があります。一方で地方は少人数体制や実習環境の制約が合格率に影響を与えています。
教育体制や受験者数の地域差が合格率に与える影響
地域別の合格率に差が出る主な理由として、以下のポイントが挙げられます。
- 学校数や受験者数が多い地域では、受験対策講座や模擬試験の充実度が高い
- 都市部は看護師求人や就職先も多く、競争意識が高い
- 地方部は少人数制で手厚いサポートが受けられる半面、受験者数が少なく合格率が安定しにくい
- 教育環境やカリキュラムの違いが、得点力の差となることも
このような背景が、都道府県別の合格率ランキングに反映されています。
地方と都市部での受験環境比較と合格率の関係
地方と都市部での合格率の違いは、受験環境や情報量の差も大きく影響します。
- 都市部では、専門学校・大学・予備校が多く、模擬試験や情報提供などの支援が充実
- 地方では、生徒一人ひとりの実習や指導は丁寧であるが、共有できるノウハウや最新情報が限られる
実際に都市部では、合格率が95%以上となる学校が多くみられ、一方で地方の一部地域は90%を下回ることもあります。特に、都市型は国家試験対策の勉強会や就職支援も手厚いため、高い合格率を維持しやすい環境です。
| 比較項目 | 都市部 | 地方 |
|---|---|---|
| 学校数 | 多い | 少ない |
| 合格率 | 高め(95%~96%前後) | 変動しやすい(88~92%) |
| 支援体制 | 予備校や模試が豊富 | 独自指導や少人数制 |
| 就職・求人 | 機会多数 | 地域密着・限られる場合も |
地域で学習環境やサポート、情報の流通に差があることから、看護師国家試験合格率には都道府県ごと、また都市と地方で明確な違いが見られます。進学時は志望エリアの合格率や支援環境も重視し、安心して受験に臨むための情報収集が重要です。
合格発表後の手続きと免許申請の流れ詳細ガイド
合格発表スケジュールと通知方法
看護師国家試験の合格発表は、例年厚生労働省の公式サイト上および各地の指定場所で同時におこなわれます。発表は正午に公開され、受験番号をもとに合否を確認します。インターネットと掲示板のどちらからも閲覧可能なため、迅速な情報収集が重要です。
特に合格者には後日、登録している住所宛に合格証書が送付されます。合格発表に合わせて「学校別合格者状況」も公開されるため、自分の出身校や専門学校、大学が全国的にどの程度の合格率だったかも確認できます。合格発表日と通知方法を把握し、スケジュール漏れのないように注意しましょう。
合格証書の受け取り方法と注意点
合格者へは郵送で合格証書が届きます。合格証書は免許申請に必須のため、到着後すぐに内容を確認してください。以下の点に注意しましょう。
- 合格証書は郵便書留で届くため、不在時は不在票に気を付ける
- 紛失や破損があった場合は速やかに出身校または厚生労働省に問い合わせる
- 合格証書には受験番号や氏名が記載されているため、受け取り後は誤字脱字、情報の正確性をチェックする
合格証書の取り扱いには最新の注意を払い、大切に保管してください。
免許申請に必要な書類・受付時間・提出先の最新情報
免許申請は各都道府県の指定窓口や保健所で受付されます。申請書類や提出先、受付時間を事前に確認しておきましょう。情報をわかりやすくまとめたテーブルを参考にしてください。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 合格証書の原本とコピー | 紛失時は再発行手続きが必要 |
| 戸籍抄本(6か月以内のもの) | 本籍地が記載されたもの |
| 申請書(各都道府県配布) | 公式サイトからダウンロード可 |
| 収入印紙(定額) | 申請料として事前に準備 |
| 証明写真(規定サイズ) | 背景無地、6か月以内の撮影 |
| 本人確認書類(運転免許証等) | 原本が必要 |
申請受付は平日のみで、9:00〜16:30が一般的ですが、地域により異なる場合があります。事前に電話やウェブサイトで確認し、早めの準備を心がけましょう。
申請時によくあるミスや注意点の解説
免許申請では下記のポイントに注意することでトラブルを防げます。
- 戸籍抄本の有効期限切れや記載内容の不一致
- 写真サイズ・背景・服装の規定ミス
- 申請書の記載漏れや書き損じ
- 収入印紙を現金と間違えて提出
- 合格証書の提出漏れやコピー忘れ
これらのミスは再訪や書類不備につながるため、事前に必ずリストをもとに確認しましょう。万が一不備があったときは、速やかに担当窓口へ連絡するとスムーズです。
免許申請は合格発表と同様に重要な手続きです。書類や手順に間違いがないかを一つずつ見直し、安心して新たなスタートを切りましょう。
よくある114回看護師国家試験における合格率関連の質問
合格基準やボーダーラインに関する質問
第114回看護師国家試験の合格基準(ボーダーライン)は、例年通り厳格に設定されています。合格基準は「必修問題80%以上の得点」と「一般・状況設定問題で合計60%前後の正答率」が一般的です。具体的には、必修問題50問中40問以上、一般・状況設定問題240問中約145点以上が求められます。ボーダーラインは年度によって数点の変動があるため、最新の数値は厚生労働省の公式発表で確認しましょう。また、ボーダーラインの決め方は、試験問題全体の難易度や全国平均点を基に決定されます。
学校別合格率や難易度に関する質問
看護師国家試験の学校別合格率は、進学・進路選択の大切な判断材料です。下記テーブルに主な大学・専門学校の合格率をまとめます。
| 学校区分 | 合格率上位校例 | 合格率 |
|---|---|---|
| 大学 | 順天堂大学、北海道大学 | 100% |
| 専門学校 | 一部上位校 | 98~100% |
| 全国平均 | – | 90.1% |
このように、合格率が100%を達成する学校も多数存在し、毎年学校別ランキングが注目されています。難易度は全国的に安定傾向にあり、比較的高い合格率を維持しています。
合格発表や免許申請に関する質問
合格発表は例年3月下旬に厚生労働省公式サイトで実施されます。合格者への通知や合格発表後の流れは下記の通りです。
- 合格発表当日に受験番号で合否確認が可能
- 合格者には、後日合格証明書が送付
- 免許申請は都道府県ごとの所定窓口で手続き
- 必要書類や健康診断書などを準備して提出
合格率についても発表時には学校別統計や総合状況が公開されるため、信頼できる公的データとして活用できます。
不合格時の対策や再受験のコツに関する質問
万一不合格になった場合でも適切な対策を取れば再受験で十分合格を目指せます。主な対策は次の通りです。
- 自己採点とレビューで苦手分野の洗い出し
- 過去問題や模試を繰り返して解く
- 試験当日の時間配分やメンタル面の見直し
- 合格率の高い専門学校・予備校の実績を参考に学習環境を見直す
再受験時は前回の経験を活かして対策を進めることが合格への近道です。
厚生労働省の公的データ活用に関する質問
厚生労働省が発表する看護師国家試験のデータは非常に信頼性が高く、合格率や学校別合格状況なども公式サイトで毎年公開されています。公的データを利用することで、学校選び・受験対策に役立つ最新情報を得ることができます。特に学校別合格率一覧、過去難易度の推移、全国平均点などは進路選択や受験計画に欠かせません。公認のデータを正確に確認し、安心して準備を進めましょう。